| ▲メインに戻る |
| ■第9節 ルナル世界の最期 |
 |
| ルナル世界は、我々の地球とはかなり異なる文明の歴史を歩んでいる。「第5節 魔法文明を考える」で語ったが、テクノロジー文明と魔法文明は、最終的には行き着く先は同じかもしれないが、その途上で歩む道のりはかなり異なる。 では、ルナル世界はどのような将来設計で運営されているのであろうか。ここでは「魔法文明」を前提として、月(=神々)の視点でルナルの未来を推測していきたい。 そして未来を知るには、まず過去を知る事から始めなければならない。 |
| ▲メインに戻る |
| ■第9節 ルナル世界の最期 |
 |
| ルナル世界は、我々の地球とはかなり異なる文明の歴史を歩んでいる。「第5節 魔法文明を考える」で語ったが、テクノロジー文明と魔法文明は、最終的には行き着く先は同じかもしれないが、その途上で歩む道のりはかなり異なる。 では、ルナル世界はどのような将来設計で運営されているのであろうか。ここでは「魔法文明」を前提として、月(=神々)の視点でルナルの未来を推測していきたい。 そして未来を知るには、まず過去を知る事から始めなければならない。 |
| ■〈源初の創造神〉の立場は? |
| この世界に、まだルナルの大地がなかった頃――― この宙域に、白い月が1つだけ、ぽかんと浮かんでいたらしい。これは、地球の天文学的に「岩石型の自由浮遊惑星」なのか、はたまた「寿命が来てとりあえず燃え尽きた白色矮星」なのか…ファンタジー世界でそれを突っ込むのはどうかと思うので、まぁ気にしない事にしよう。 この通称「月」には、1人の意志が宿っていた。 |
 |
| 神話では〈源初の創造神〉と言う名で伝わっている、ルナルの創造神である。 創造神を「第5節」で解説した魔法文明に当てはめると、登場の時点で既にML(マジック・レベル)10に匹敵する存在だったと思われる。宇宙全体の記録が書かれているという「アカシック・レコード」とアクセスして全ての知識に精通し、天体と一体化して膨大な量のマナを操り、創造と破壊を自在に行える―――まさに創造主と呼ぶに相応しい存在である。 なお、魔法文明においてML8以降の魔術師たちは「純粋知性体」(250cp 「ガープス・サイオニクスp48参照)の特徴を獲得した情報統合思念体であり、物理的身体を持たない(当然、寿命もない)。ただし、必要になれば自身をイメージする肉体を生成し、他の人間に混じって自由に活動できる。 情報統合思念体にもランクが存在し、それは主に知識の量と扱えるマナの量で決まる。初期のそれは、肉体があった頃の魔術師の延長でしかなく、アカシック・レコードへのアクセス方法なども知らないため、認識している知識の量や扱えるマナの量は少なく、せいぜい小神レベルである。 そんなランク付けの内、〈源初の創造神〉は出現時から最強の存在だった。創造神がどのような経緯で生まれたかは定かではないが、「孤独に苛まれていた」という経緯から、「同族」の概念がなかった可能性が高い。 ゆえに、どこかの惑星の高度文明出身者ではなく、宇宙に流れる情報に意志が芽生え、直接的にこの状態で生まれてきた存在であろうと推測できる。 ただ1人で生まれ、周囲には分かり合える存在がおらず、孤独に悩まされた創造神は、あらゆる次元を見通す偉大な知覚でもって、自分と同等の、分かり合える存在を求めて宇宙全体を見渡した。 そして、それを見つけた。 ところがそれは、既知宇宙にはいなかった。それらは、ルナルの神話において「至高なる輝きの地」と称される世界―――おそらくは文明の終着点となる「宇宙の外」にいたのだろう。そこには創造神と同格で、かつ分かり合える存在が集まっており、さまざまな新規宇宙の作成を行っていたのではなかろうか。 つまりルナルの創造神は、「友達がやってる宇宙創造プロジェクトに参加するため、既知宇宙から旅立った」というのが、管理人個人の推測である。 |
 |
| 創造神は、さっそく準備に取り掛かった。 創造神は偉大な力を備えていたが、自身(白き月)が保有するマナだけでは、どうやら足りなかったようである。ゆえに旅立ちにあたってゲート作成のエネルギーを確保するため、ルナルの大地を作った。そして、サーバント(奉仕者)として「古の三者」(〈源人〉〈龍〉〈天使〉)と呼ばれる存在を生み出し、エネルギーを充填する作業に没頭させた。 当時のルナルには恒星と呼べる存在がなかったらしく、創造神自らが輝いていたという。 そして十分なエネルギーを充填した後、白き月のコアだけを抜き取って太陽を生成し、それを異次元ゲートとして、創造神は既知宇宙から脱出する。 しかし、大半のサーバントたちは一緒に次元跳躍するだけの能力がなかった。創造神は「いつか自分を追ってくるように」と言った。あるいは「迎えをよこす」と言い残したともいう。 真相は定かではないが、とりあえず偉大な創造神は自身の寂しさを慰める事を優先し、この世界からは去っていった。 〈源人〉は〈天使〉と協力して、何とか追いかけようとする。一方、〈龍〉たちは創造神の言葉を信じ、迎えが来るまで眠ることにした。 だが、いくら待てども、創造神の迎えが来ることはなかった。 |
| ■計画になかった帰還者たち |
| 創造神は次元移動後、向こう側(至高なる輝きの地)から、儀式の際に残った彷徨いの月を通してルナル世界を見ていた可能性は高い。なぜならば、ルナルに介入したと思しき行為があったからである。しかし、直接的に迎えを寄こす事はなかった。 ―――双子の月がやってくるまでは。 残されたサーバントたちが「至高なる輝きの地」にすぐに招集されなかった理由は、次のようなものが考えられる。 「肉体に縛られている低レベルの生命体では侵入不可能な領域だった」 「至高なる輝きの地で行われている事が新規宇宙の創造事業だった場合、まだそのランクに達していないレベルの存在が到達したところで、できる事は何もない」 …要するに、次元移動には太陽という超高密度エネルギー・フィールドをくぐらねばならない事から、物理的身体に依存しているレベルの者ではそもそも抜けられないこと、低次元の存在にとって輝きの地が「理想郷でも何でもない」と知った事などから、創造神は迎えを寄こす事を躊躇したと考えられる。 創造神のルナルへの介入に関しては、「改定版ルール 第4章 彷徨いの月の種族」の編集手記に推測を記してある。簡単に書くと、以下のとおり。 『銀の月と〈龍〉との抗争で荒廃したルナルを再生するため、緑の欠片を投下した』(エルファ誕生のきっかけ) 『黒の月によって滅亡しかけているルナルを救うために、双子の月を派遣した』(エルファの失敗のフォロー) …以上は、創造神が次元を超えて直接介入したイベントである可能性が高い(少なくとも後者に関しては、小説にて遠回しな表現でそう書かれている)。 |
 |
| いずれの介入も、創造神にとっては「予定外」であったようだ。そうでなければ、直接介入するような事はなかったろう。世界を創造するレベルの偉大な神格であっても、不測の事態というものは存在するらしい。 この二つは密接につながっていて、創造神が最初に行ったと思われる介入「緑の月の欠片の投下」イベントは、紆余曲折を経て「黒の月を生み出す」という、とんでもない結果を発生させてしまった。 結果論ではあるが、一連の因果律を発生させてしまった最初の起点(原因)は創造神のささやかな救援行為であり、全く責任がないとは言えない―――というか、少なくともML10の超越存在であれば、ある程度の未来予知はできたはずである。なれば、創造神は一連の出来事を敢えて見守っていた可能性がある。 創造神が、エルファの愚行を黙って見守っていた理由は、彼らが自力で発展し、輝きの地へと至るくらいの知恵を持った賢明な種族であると、エルファたちに可能性を見出したからではなかろうか。エルファたちは創造神の「支援物資」とはいえ、それを使って自力で「月」を作り出し、自ら崇める天体を創造したのだ。ならば、自力で輝きの地へ到達する事も、あるいはできると期待したのだろう。 だが残念な事に、彼らは自分たちの力だけで世界を再生した(と思い込んでしまった)事で天狗になってしまい、自らの力量を見誤っていたようである。そして「誰も止められない黒の月を呼び出してしまう」という、取り返しのつかない大失態を演じてしまったのだ。 創造神もおそらく失敗は想定していたが、まさか失敗の結果が「黒の月に変貌する」とは、予想もしていなかった可能性が高い。もし予測のうちにあれば、さすがに何らかの偶然を装って止めたはずである。 ここに至って、創造神は「少々早すぎるが、手元のサーバントを派遣して助けるしかない」と判断したようである。そして、黒の月が発生してからわずか20年ほどで、双子の月の神々が派遣された。 20年というと、人間の視点ではそれなりの年数かもしれないが、宇宙規模の視点で見ると、ほとんど「集中行為なしでターン冒頭に瞬間発動」に近い超高速対応である。創造神ともあろうものが、よほど慌てたに違いない。 そしてそれによって、ルナルの将来設計も大きな修正を余儀なくされたのである。 |
 |
| では、創造神の元々の計画は、どうだったのだろうか? おそらく、残されたサーバントたちが自力で「至高なる輝きの地」まで到達する事を期待し、直接的には手を出すまいと決めていたのではなかろうか。 古の三者、特に〈源人〉に関しては、かなり高度な自己判断能力と、輝きの地に至るまでに必要な素養(知力や魔法の素養)は十分に持たせた上で生み出したという自負は、おそらくあっただろう。実際、〈古の三者〉の中でも上位の存在は、創造神の旅立ちに同行できるだけの能力を有していたのだから。 そのため、創造神がルナルの大地を去り、双子の月を派遣するまで、最低でも数万年、あるいは10~100万年単位の時間が経過し、その間はずっと見守っていたはずである(具体的な経過年数は、ルールブックの設定には全く存在しないので、あくまで予想である)。 だが、当初は「創造神を自力で追いかけよう!」と頑張っていた〈源人〉たちも、それが途方もない技術発展の先にあると知り、おそらくは途中でモチベーションを失い、儀式再現を止めてしまった。創造神が去った直後、制御を失った太陽が暴走し、白の月の時代の文明物をことごとく焼き払ってしまったダメージの影響も大きい。 それから数万年後か数十万年後に、創造神の支援行為が元で〈源人の子ら〉の一部がエルファとなり、再び期待をかけたものの、今度は取り返しのつかない失敗をしでかしてしまった。 また、残された白き輪の月に留まった〈天使〉たちは、生命というよりも命令を忠実に実行するだけのオートマトン(自動人形)に近い種族だった。そのため、〈源人〉のように自発的に何かするような意志(自律プログラム)など、最初から組み込まれてはいなかった。 そして〈龍〉に至っては「自身は最強の存在=これ以上努力しても無駄」という、ドラゴンボールのフリーザみたいな考えに至ったのか、最初からニート気質全開で「創造神が迎えに来るまで寝て待とう」というありさまであった。 結局のところ、月の加護の下に生まれた古の三者という存在は、月の「導き」がなければ、より上位の存在に発展できなかったのだ。 仮に、黒の月が到来せず、双子の月を派遣する必要がなかったとしても、創造神が何らかの介入せねば、残された彼らが自力で創造神の御許へと到達する事は、不可能だったと言わざるを得ない。 |
 |
| ■神による技術提供 |
| 創造神がおわす「至高なる輝きの地」が宇宙の外側と仮定すると、そこには空気や水や重力、それどころか時間の流れすらもなく、物理的身体を持っている状態では、現地への到達は不可能である。そのため、最低でもML8の「情報統合思念体」になる必要がある。 「ガープス・サイオニクス」のルールによると、人は死ぬと自動的に「霊体」(-25cp)となるが、これは霊界に縛られた存在であり、この状態では物理的な障害こそ受けないが、認識できる世界はごく狭い範囲に留まってしまい、物質界に影響を与える手段もごくごく限定されてしまう。そのため、上位互換である「純粋知性体」(250cp)を獲得せねばならない。 |
 |
| 魔法文明においては、「ガープス・マジック」の情報伝達系、精神操作系、死霊系呪文を駆使することで、そのような存在に意図的になれる技術が開発され、魔術師たちは自発的にこの特徴を得られる(当サイトの魔法文明の発展はそういうものだろうと想定している)。 一方でテクノロジー文明においては、TL11以降の超能力者(テレパシー能力者)が、何らかの肉体的死亡状態が発生した際、偶然にこの特徴を得る可能性があるとしている(これも当サイトが勝手に決めた設定で、実際のところは未知数である)。 その他、ルナルの〈源初の創造神〉のように、魔法かテクノロジーかは関係なく、何らかの拍子に宇宙を漂っている情報が直接意思を持ち始め、偉大な存在として生まれてくることもあるのかもしれない。 そしてルナル世界においては、死後に月へと至ってガヤン神が開催する法廷に立ち、その後の進路が決定されるとされる。十分に修行を積んだとされる者だけが、神より「純粋知性体」になる手解きを受け、ML8の「情報統合思念体」になる事ができると想定される。 そして、太陽という次元ゲートの前に立ち、創造神が定期的に行使する召喚魔法によって「輝きの地」へと至るのだ。 |
 |
| 本来ならば、〈源人の子ら〉が自力で至るべきである。 実際、〈源人〉の力を受け継いで生まれたウィザードたちは、死後に白き輪の月に残された創造神の行動記録とアクセスし、自力で情報統合思念体へと進化し、異次元ゲートの前まで到達するものと思われる。 だが「迎えを寄こす」といった手前、それでは無責任であるし、古の三者の多くは、ある程度の「導き」がなければ途中で挫折してしまう。また〈龍〉のように、最初から創造神の迎えを当てにしている連中すらいる。 さらに、黒の月が跋扈してしまったこの世界に長く居続けるのは危険であった。 仮に黒の月が現れなかったとしても、同種の危険がルナルの大地を襲う可能性は常にある。黒の月以前にも、銀の月の神々という完全にルナルとは異質の存在がやってきて、堂々と侵略行為を開始したという実例もあるからだ(その時は、世界に残っていた〈龍〉たちが戦ってくれたおかげで助かったが…)。 よって、創造神としては古の三者の回収を優先しているものと思われる。で、あるならば、おそらくルナルの文明がこれ以上発展する事もないように見える。しかし回収が遅れた事で、さらなる問題が発生していたのである。 |
| ■多様化したサーバントたち |
| 古の三者の回収優先に予定変更した創造神だったが、少々遅すぎた。 というのも、古の三者のうち、〈龍〉は既に銀の月との戦いで互いを封印する状態となっており、これを動かすには、まず銀の月の神々をどうにかせねばならない。 なお、これに関してはリプレイ「月に至る子」(3部作)において、月に至った主人公たちが「銀の月の神々のために新規ワールドを作成する」ことで、ある程度の解決の目途は立っている(詳細はリプレイ参照)。 元々、居場所を探して放浪中だった銀の月の神々は、これによって自分たちの世界を得て〈龍〉との和解が成立し、再びそれぞれの道を行く事になるだろう。 また、〈源人の子ら〉のうち、力を求めて銀の月を崇めるようになった者たちに関しては、既に遺伝子レベルで銀の月の神に忠誠を尽くす存在となっており、これを強引に引き離して輝きの地へ連行したところで、彼らにとっては幸福とは言い難いであろう。 彼らとは別に、二つ目の緑の月を作り出そうとして黒の月を呼び出してしまったエルファたちだが、彼らが二つ目の月を作ろうとしたのは「ルナルを植物で覆い尽くすため」―――つまり、彼らは既に精神的に独立し、ルナル当地で自らの理想郷を作ろうとしていたのであって、別に輝きの地を目指していたわけではなかった。 彼らが奉ずるところの〈円環〉の思想を見ても、現状を維持する事が目的であって、現状の改善・さらなる発展の要素が見受けられないからだ。 そして――― 黒の月を崇めてしまった連中に関しては、既に「滅びを崇める忌むべき存在」である。これらを輝きの地へ連れて行くわけにはいかない。 |
 |
|
このように、〈源人の子ら〉は自力で輝きの地に至る事を止めた後、それぞれが自分の意志で理想郷を追い求めており、もはやこの時点において、創造神の元に戻る事が必ずしも創造神とサーバント全員にとっての幸せとは言い難い状況になってしまった。 また、サーバントと創造神の意識レベルの違いもある。 創造神が輝きの地を目指したのは、彼が生まれつきのML10の超越存在であり、仲間と共にあるためには次元の壁を超えるしかなかったからである。彼は「孤独を癒すため」に輝きの地を目指したのである。 しかし、サーバントとして生み出された者たちには同格の「仲間」が存在しており、別に輝きの地に至らずとも、創造神のような孤独感は存在しないだろう。 つまり、創造神の傍におらずとも、仲間と共に過ごす事で安寧を得られるのであれば、無理に進化してまで輝きの地に至る必要などなかったのである。 こうした立場による意識レベルの違いを、当初の創造神は分からなかったのであろう。 なぜならば、彼は最初からML10の偉大な存在として生まれてしまったが故に、自分より格が低い存在に関して、知識としては知り得ても、自身の感覚として想像する事が難しかったからである。 |
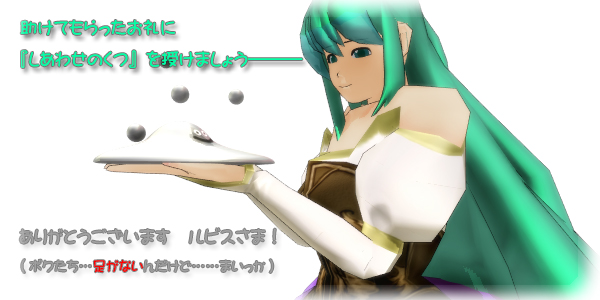 |
| 例えば、我々のようなルナルの創造神よりも数段未熟な地球のホモ・サピエンスであっても、自分より知能が低い小動物や、果てはウイルスや細菌などといった微生物が持つ意識がどのようなものであるのか、正しく認識する事はできない。そうした事は、観察によって外部から想像するしかない。 創造神のサーバントに対する認識も、同じような状況だったのではないだろうか。 サーバントは、すでに創造神の手元から離れ、独自の存在として自らの足で歩み始めた。ゆえに、創造神の理想を一方的に押し付けるわけにはいかなくなった。 しかし、そういった事情を考慮してなお、サーバントたちをルナルの大地から救出せねばならない理由が、少なくとも創造神の中にはあった。 それは、太陽の寿命である。 |
| ■ルナルの最期 |
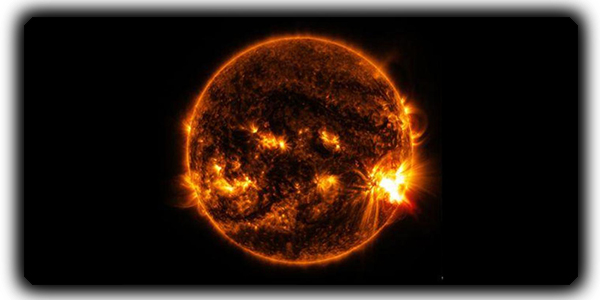 |
| 創造神が異次元ゲートとして使用した「太陽」は、おそらくは我々の地球の太陽と同規模の主系列星であり、恒星のはずである。 当然ながら恒星である以上、星としての寿命が存在する。 我々が属する太陽系の恒星「太陽」の寿命は約100億年であり、水素の原子核融合を終えると、太陽サイズの恒星ではヘリウム以降を核融合するだけの出力(重力)を持たないため、活動を停止する。 ルナルの太陽も同様のサイズだとすると、たとえば地上で自らの理想郷を見出したエルファたちが、輝きの地を目指さずに繁栄したとしても、恒星の活動停止→一時的な膨張→ガスの拡散の工程を経て星全体が焼却され、生命活動も強制終了する事になる。 100億年という期限は、400年程度の(宇宙的視野で見れば)短い寿命をつないで繁栄するエルファにとっては、十分な活動期間なのかもしれない。だが、恒星の崩壊と共に、いつかルナルの大地も終わる。その時、たまたま終焉期に生まれてしまった者たちは、哀れとしか言いようがない。彼らには何の罪もないのにも関わらず、悲惨な最期を迎える事になるからだ。 また、銀の月の元素神に忠誠を誓い、創造神の御許を離れた眷属たちも、元は〈源人の子ら〉であり、創造神からすれば我が子同然であるが、一方で他所の星系からやってきた銀の月の元素神たちは、ルナルの生命体の愛着があるとは言い難く、感情面での気配りなど無きに等しい(自立心や個性の露骨な軽視)。 ゆえに、恒星の滅亡と共に見捨てられ、消滅する可能性が高い。あるいは「我らの新たな旅立ちの前準備として、(どうせ死ぬなら)生贄となって我らに奉仕せよ」などと言い始めるかもしれない。 銀の神々はそうやって眷属を食い潰し、また別の星系に移動すればいいだけだろうが、古の三者に「助ける」と言い残して去った創造神としては、亜流となった存在だとしても、〈源人の子ら〉が置き去りにされて悲しみの中で滅亡していく様を黙って見過ごすことはできない。 そこで、創造神と彼が派遣した双子の月の神々は、二重の策を取った。 一つ目は文明開化である。 まず、双子の月に転向した人間とドワーフ以外を通じて、ルナル全体に文明という恩恵を与え、自分たちだけでもこの星から脱出できるだけの文明を持たせようとしたのだ。 魔法文明では8レベルで「情報統合思念体」へと進化し、物理的身体なしでも存在し続けられるようになる。一方、テクノロジー文明でも8レベルから宇宙開拓事業が展開されるため、ゆくゆくは母星が崩壊しても他の星へ移り住む事で絶滅を回避できる。 すでに自立した〈源人の子ら〉は、たとえ死後に情報統合思念体への進化を約束しても、輝きの地への移動を望まないかもしれない。しかしそれでも、種族全体がこの星から旅立てるだけの文明を持たせておけば、もう二度と会えないかもしれないが、生き永らえさせる事はできよう。 もう一つは、黒の月の消滅である。 今後、〈源人の子ら〉がどのような道を行くにせよ、黒の月だけは絶対に消滅させておく必要がある。しかし困った事に、双子の月の神霊力をもってしても、黒の月を封印状態にしておくのが精一杯で、その「ブラックホール」と思しき天体を消滅させる事はできていない。 |
 |
| その理由として考えられるのは、ルナルの大地そのものの特性である。 〈悪魔〉は〈天使〉と同じくエネルギー生命体であり、マナそのものが意識を持った状態で存在していると言い換えても良いだろう。〈悪魔〉たちはしぶとく残っているのは、ルナルの大地からマナを吸いとる事で、黒の月という名の暗黒世界へのゲートを維持し続けているからではなかろうか。 元々、ルナルの世界は、「至高なる輝きの地」へ至るためのゲートを作るために必要なマナを追加生産するための「発電所」であった。その機能は、創造神が去った後も残っていて、それを〈悪魔〉に利用されているのではないか。 要するに、エルファが第二の緑の月を作ろうとした儀式のファンブル結果は、黒の月の側から「ベインストーム」などといった形で無理やり維持コストをルナルから引き出す事で、いまだ持続しているのではないか。 ちなみにリアド大陸には、「歪みの沼」「〈悪魔〉海」「魔性湖」と呼ばれる〈悪魔〉に完全制圧された3つの土地が、〈悪魔〉戦争後から1000年経った現在でも残されており、誰にも邪魔されずにベインストームを引き起こし、マナを盗み取るのに最適の地と言えよう。 (ベインストームとは「ガープス・ベーシック第4版」のインフィニティ・ワールドに登場する「自然現象」の1つ。次元を超えた2点間で唐突に物質が空間ごと入れ替わる台風のような気候現象。完全な球状で発生し、中身をまるまる置き換えてしまう。魔法由来の現象と推測されているが、魔法ですら制御不能のため詳細は不明。「キャンペーン」p507参照) この儀式魔法の効果を強制中断するためには、「マナを断ち切る」以外の手段はないと思われる。つまり、「ルナルから魔法を消滅させる」必要があるわけだ。 ところが、今まで散々魔法の力で文明を維持してきたルナルの人々が、いまさらマナを消し去られても大変困るだろう。それにとってかわる「手段」がない限りは。 そこで、魔法を使わない「テクノロジー文明」が生きてくるわけである。 双子の月の神々が、人間やドワーフの扱える呪文を信仰ごとに厳密に管理し、自在に使わせない最大の理由は、「今はまだ〈悪魔〉戦争直後の復興のために残しているが、将来的には完全に魔法なしの状態にするつもりだから」ではないだろうか。 魔法文明である限り、〈悪魔〉が出てくる「黒の月」という名の魔法的なブラックホールは延々と居座り続け、いつの日か人々は〈悪魔〉の勧誘に負けて、黒の月から力を引き出すようになってしまい…そうなればルナルは、確実に破滅するだろう。 そうした後顧の憂いを絶つためには、魔法を使わない文明を発展させ、テクノロジーを用いた宇宙開発時代まで持っていくしかない。 無論、銀の月の元素神がやったように、いきなりTL7~8の技術を眷属に渡しても、受け取った眷属たちは自ら築き上げた基礎理論を持っていないため、その技術を理解する事はできない。理解できない超技術は、マニュアル(聖典)通りに運用する事はできても、修理は出来ないし発展させる事もできない。 現実問題として、はるか昔に銀の月の神々がやってきて、その折に眷属となった〈源人の子ら〉(翼人、爬虫人、〈多足のもの〉、〈姿なきグルグドゥ〉)は、TL7相当の技術供与を受けたはずなのだが、それから数万年は経っているであろう現在のルナルにおいても、技術レベルは一向に変わっていない。 銀の月の眷属は、必要であれば神が直接的に「最適解」を寄こしてくるし、眷属は自分で考える必要がそもそもない。そのような環境で生きる者にとって、自分で考えて理解し、発展していく必要性などなく、ただ神の意志に従って奉仕奴隷として活動してればいいのである。 しかしそれでは、ルナルなき後に輝きの地へ行かない選択した〈源人の子ら〉にとって、この広大な宇宙で生き延びる事は困難であろう。 そのため双子の月の神々は、人間やドワーフたち自身の力で、ゆっくりとだが確実に自分たちの力で技術を習得して行くのを、辛抱強く待ち、段階に沿って導く必要がある。 また、双子の月以外を崇める〈源人の子ら〉にも、遠回しにそうさせる必要がある。人間、ドワーフに〈源人の子ら〉のリーダーになって貰う事で、他の月の信者も引っ張ってもらうのだ。 実際、彷徨いの月の種族は人間社会と深く交わり、それに釣られて徐々に文明化してきている。エルファもまた、フェルトレ氏族の長老が双子の月に探査の目を向けた際、「螺旋の思想」をインスピレーションとして受け取っており、ただ現状を維持して同じところを回り続けるのではなく、螺旋状に登って発展つつ維持していくように啓示を受けている(この啓示はおそらく双子の月が与えたものだろう)。 |
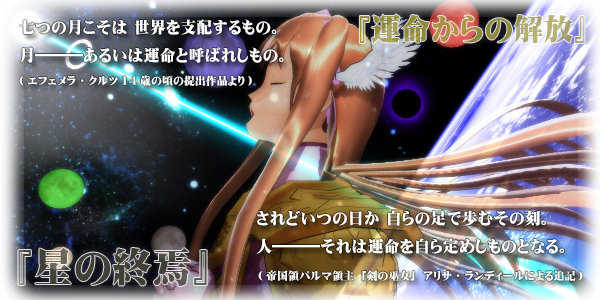 |
| 創造神が派遣した双子の月の神々は、自分たち以外の信者である〈源人の子ら〉も、可能な限りまとめて救済するつもりなのだ。そして、それを成し遂げて初めて、創造神が古の三者に対して約束した事を完遂させた事になる。 どんなに時の流れが〈源人の子ら〉の生きざまを変えようとも、〈源初の創造神〉は自身の分身たる子供たちを、決して見捨てたりはしないだろう。 |